債権回収物語vol.10

vol.9より続く。
競売の話なんですね。当事者目録ができあがりましたという段階です。
次に、「担保権、被担保債権、請求債権目録」を作ります。
これがまた面倒なんですね。
つまり、いくらを請求しますか?ということです。
元金は分かりやすいです。間違うことはないです。
間違いやすいのが、利息と損害金です。
これは、銀行内部のシステムで出力したものをそのまま書くと、裁判所から「数字が違う」と言われて訂正を求められることがしばしば起こります。
なぜかというと、銀行の原則は365日日割り計算で利息を計算しますが、裁判所の原則はそうではないことに由来します。
裁判所の基本ルールは、閏年の利息は366日で割れ、ということなんですね。
ですので、銀行のシステムで2012.9.1〜2012.9.30の利息を計算するときには、
元金×年利率×30日÷365=利息の金額
となりますが、裁判所ルールでは、この年は閏年なので、
元金×年利率×30日÷366=利息の金額
となり、元金が大きいと利息の金額が変わってきます。
そして、分母が365日日割り計算のほうが小さいということは、365日日割り計算のほうが利息が大きくなりますので、「あんた、請求しすぎだ」と裁判所から電話がかかってくることになるわけです。
もっとも、最近は登記簿に「利息 ○.○%(365日日割り計算)」と登記してあることが多いです。これだと対抗力があるので、365日で計算しても、裁判所から文句は出てきません。
利息と同様、損害金も同じ問題があります。損害金も「損害金 ○.○%(365日日割り計算)」と登記してあれば、ぜんぶ365で割れば済む話ですが、昔の債権だとそこまで登記していないのが多いので、計算に苦しむはめになります。
だいたい競売申立のときに苦労するのはこういうところだと思います。
司法書士に外注する銀行もあるみたいですが、結局は請求債権額を確認しなきゃならないので、手間は変わらないと思いますね。
競売申立書を裁判所に郵送して、1週間くらいすると、予納金の振込用紙が送られてきます。そこに振り込んで、しばらくしたら「競売開始決定書」が届きますので、それから競売事件が進行します。
で、ただちに差押の登記がなされます。ここで時効が中断しますので、時効中断のために(売れないと分かってて)競売をすることもあります。
競売で失敗した事例を次回ご紹介しましょう。農地特有の問題です。
続く。
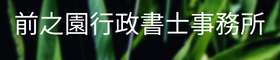
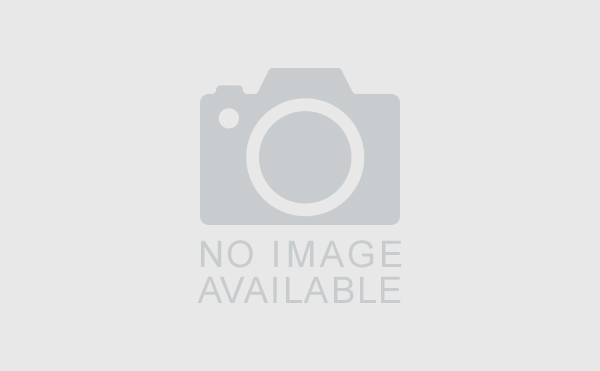
板倉大輔 liked this on Facebook.
Takashi Miyamoto liked this on Facebook.
Kenichi Mashima liked this on Facebook.