債権回収物語vol.5

vol.4に続く
競売するにあたり、まず現地を見に行く。
農家を対象としており、秋田は10人農家がいれば9人はコメ農家みたいなところがあるから、担保といってもほとんど田んぼだった。
田んぼを見るとき、ポイントがいくつかある。
一つは、形と広さだ。せめて1反くらいはないと売れそうにない。
1反とは、10アール、1,000㎡、333坪である。
よく、テレビで300坪の超広い物件!なんてやったりしているが、農家的には300坪なんて問題にならない狭さだ。
基盤整備といって、区画整理をしてある土地であれば、だいたい3反で区画されている。広いところでは、5反区画のところもある。
大潟村にいくと、1町歩区画だったりする。1町とは1ヘクタールのことだ。
形も長方形でないと、トラクターが入りにくい。三角形だったりすると、これも農家がいやがって買い手がつきにくい。
基盤整備されているところのポイントとしては、土地改良区の賦課金を滞納しているかどうかが問題となる。
土地改良区とは、いわば区画整理事業の補助金の受け皿みたいな団体である。農業に関わりの薄い人にとっては、これが団体を意味することすら知られていないが、農業においては、極めて重要なステークホルダーの一つである。
この区画整理事業(土地改良事業というのが普通だが)は、ほとんどが補助金だが、一部は自己負担がある。その自己負担分は、農家から、賦課金として徴収する。これを延滞している人がいるのですね。
そして、こちらを延滞しているような人は、だいたい土地改良区の賦課金も延滞しているのである。
そうすると、その賦課金は、人についているのではなく、土地についている(土地改良法にそう書いてある)ので、土地を買った人が延滞している分も払わないといけないのですね。
そのため、土地改良区の賦課金の延滞分が、競売にかける土地の評価額から引かれて評価することがある(裁判所によって違うようだが)。
そうなると、土地の評価がただでさえ競売で安いのに、余計安くなるわけです。
するとですね、競売するのにもお金がかかるので(これはあとで述べる)、費用倒れという事態が発生するのです。
そうなると、競売は中止になってしまい、一方、競売のため払った費用は返ってこないので、「損するだけ」になってしまうのですね。
だから、競売しようにも競売できんよ、ということがあるわけです。
ただまあ、「だから担保は処分できない」という疎明の資料にはなります。
(つづく)
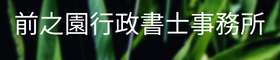
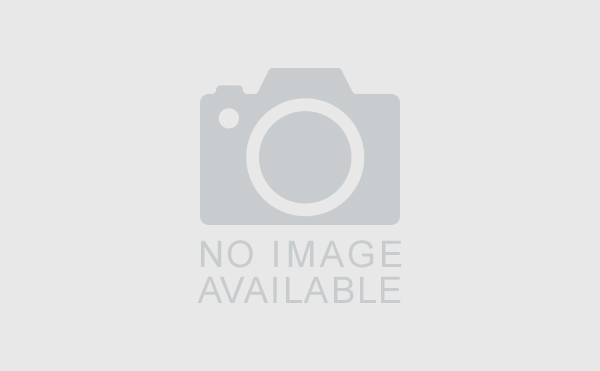
Miki Ito liked this on Facebook.
Kenichi Mashima liked this on Facebook.
高木大路 liked this on Facebook.
Kimihito Abe liked this on Facebook.
Kenji Nakamura liked this on Facebook.
Takashi Miyamoto liked this on Facebook.
Tatuya Maruyama liked this on Facebook.
Takeo Hiruma liked this on Facebook.
Masahiro Sone liked this on Facebook.
Hisao Seki liked this on Facebook.
Kouki Nagata liked this on Facebook.