債権回収物語vol.9

vol.8より続く。
物上保証人が亡くなっている場合の話です。
まず、亡くなった方の戸籍謄本を取ります。
これは、借用証書があれば、市役所に行って入手できます。
で、戸籍謄本は、何度か一斉更新されています。これを改製といいます。
改製がたとえば昭和55年だとしますと、昭和55年以前に除籍された人(=結婚した娘など)は、新しい戸籍謄本には出てこない仕組みになっています。
ですので、戸籍謄本の一番新しいやつだけをとっても、他に相続人がいる可能性があるわけです。
それで、改製前のものも入手する必要があります。これを改製原戸籍といいます。「はらこせき」と読む人と「げんこせき」と読む人がいるみたいです。
で、役所から戸籍をもらうときには、「その人が生まれてから死ぬまでの全部の戸籍を下さい」と言わなければなりません。
そうすると、全ての戸籍謄本を入手できます。
そして、それをもとに家系図みたいなものを作って行きます。相続関係図と言われます。
次に、その相続人の戸籍謄本も全部取ります。相続人が亡くなっている場合もあるからです。相続人が亡くなっていると、その子が相続人になります。代襲相続といいます。
で、こんなのを作っていると、相続人が14名もいる。。。というものもありました。
次に、相続分を計算しなければなりません。
普通は、配偶者が1/2、子ども全員が1/2ですが、子どもがいない場合はまた別になってきます。
相続人が14人もいると、相続分の分母も128分の・・・とかいう話になってきます。
それから、相続人の住所も調べる必要があります。
これは、戸籍の付票というものを入手すれば、最新の住所が分かりますので、そこの役場に住民票を請求して終わりです。
相続人が14名もいる事件になると、住所が全国各地になります。いきなり見ず知らずの遠い親戚の土地が競売になったという通知が裁判所から来たらみんなびっくりするんじゃないかなと思いますが。
こうして当事者目録を作成していきます。
続く。
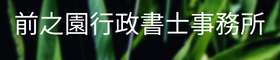
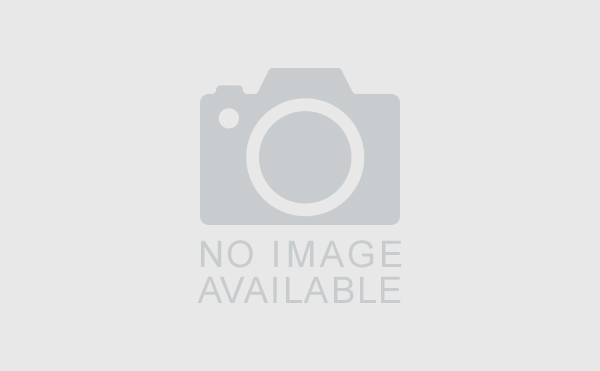
Kenichi Mashima liked this on Facebook.
Tatuya Maruyama liked this on Facebook.
宮崎俊幸 liked this on Facebook.
板倉大輔 liked this on Facebook.
Hiroichi Matsushita liked this on Facebook.
Takashi Miyamoto liked this on Facebook.